Workplace看護部紹介
看護部理念
南予の中核病院として、患者さまの人権を尊重し、やすらぎを与え、信頼される看護をめざします。
基本方針
- 1. 患者さまの人権を尊重し、思いやりのある看護を提供します。
- 2. 快適な療養環境を整え、安全・安楽な看護を提供します。
- 3. 高度医療に対応できる専門的知識・技術を磨き、質の高い看護を提供します。
- 4. 他職種と協働し、患者さま中心のチーム医療を提供します。
- 5. 地域の医療・保健・福祉と連携し、継続した看護を提供します。
平成25年4月1日改定
令和7年度 看護部目標
- 1. 看護職員の働きがいを高める環境をつくる。
- 1. 患者の人権を尊重し、倫理的課題を認識しながら、患者中心のケアを実践する。
- 1. 災害拠点病院として、災害時(災害・感染)に役割が果たせる看護部の体制を構築する。
各種体制
看護体制
看護配置
一般病棟
10:1
NICU
3:1
救命救急センター
- ICU
- 2:1
- HCU
- 4:1
看護方式
固定チームナーシング
勤務体制
- 病棟 2交代制(一部3交代制)
- 手術室
- 放射線科
- 内視鏡室オンコール制
- 日勤
- 8:30 ~ 17:15
- 夜勤
- 16:30 ~ 9:00
- 準夜勤務
- 16:30 ~ 1:15
施設基準
一般病棟用(必要度Ⅱ):急性期一般入院料4
スタッフ
| 看護部長 | 久米 理恵 |
|---|---|
| 副看護部長 | 加藤 奈美、佐野 郁 |
| 看護要員 |
(計440名) |
4西病棟【整形外科・呼吸器内科】
- 呼吸器内科患者や、整形外科の急性期からリハビリ期の患者の看護を行っている。
- 高齢者が多く、独居や介護者の高齢化により、退院支援の必要な患者さんが多い。そのため、医師やMSWなど多職種と連携を図り、退院調整や支援を積極的に行っている。
- 看護スタッフの平均年齢は38歳で男性看護師が6名と多く、また育児短時間勤務など子育てをしながら働いているスタッフもいる。
- 看護スタッフで協力し、ワークライフバランスがとれた働きやすい職場環境を整えられるように取り組んでいる。
5東病棟【脳神経外科・皮膚科・形成外科・口腔外科】
- 脳神経外科病棟31床と結核・感染症9床を併設した病棟である。
- 脳神経外科は、意識障害・運動感覚障害・失認失行・高次脳機能障害を合併している患者が多く、セルフケア能力に応じた看護を実践している。毎月1回医師・看護師・PT・OT・ST・MSW・管理栄養士による多職種リハビリカンファレンスを実施し、情報を共有することで日常生活動作の向上や維持、今後の方向性や目標を医療チームで連携しサポートしている。
- 口腔外科患者には、クリニカルパスを使用し、医療の質の効率化と向上を図っている。
- 結核・感染症病棟は、陰圧管理の病床であり、感染症患者のスムーズな受け入れができるように取り組んでいる。また、新型インフルエンザ発生時の受け入れ対応について、年に1回保健所と連携し多職種で訓練を行っている。
5西病棟【消化器内科・内分泌内科】
- 消化器内科、内分泌内科の混合病棟である。
- 内視鏡検査・処置は年間700件を超え、予定入院で検査を受ける患者や緊急入院で、処置を受ける患者の不安を軽減し、安心して検査・処置が受けられるよう心のこもった質の高い看護を実践している。65歳以上の患者が約75%を占めており、疾患だけでなくADL援助や、せん妄・認知症ケアを必要とする患者が多い。そのため入院時より患者家族の希望を確認し、患者の状態に応じ退院を見据えた看護実践を行い、患者家族の意向に沿った退院支援に努めている。
- 消化器内科は、急性期患者だけではなく、化学療法・終末期・緩和ケアの患者も多く、がん患者の精神的看護や化学療法の副作用に関する看護を実践している。
6東病棟【産婦人科・小児科・外科・NICU】
- 産科と婦人科・乳腺外科・小児科の混合病棟である。近年、少子化が進み他科の入院率が7割と高まり、助産師が助産業務以外を担い、看護技術の向上と病棟看護師との連携・協働が必須となる現場である。
- 分娩数は年々減少しているが、南予地域の周産期母子医療センターとしての役割は継続して担っている。
- 分娩件数の減少に伴い、助産師は産科以外の受け持ち患者の看護や他部署への応援業務を行い、外来保健指導や母乳外来、また産後ケア事業も継続し、幅広く活躍している。HPの更新や、電光掲示板による産科の紹介を行い、お産を増やす活動を継続し、中でもWelcomeフォトやマタニティペイントは母親に好評である。
- 周術期ケアに加え、乳腺外科化学療法も年々増加しており、助産師ががん化学療法の業務にも携わり、女性の身体そして命の誕生に関わる専門家として、若年がん・妊孕性問題に対して対応も行っている。多職認定看護師や臨床心理士、また地域連携室看護師と連携をとり、その人らしさとは何かを常に考え、良質で安心と信頼の得られる医療の提供を目指している。
NICU
- 新生児特定集中治療管理料2を算定し、南予圏域唯一の7新生児入院施設として、31週かつ1500g以上の早産や、低出生体重児、呼吸循環障害や、感染症、先天性疾患、母体合併症を有する児に対する集中ケアを実施している。
- 主治医や臨床心理士、産婦人科病棟と連携を図り、受け持ち看護師を中心に母児の愛着形成や退院後を見据えた家族指導を心掛け、信頼される家族看護を目指している。
7東病棟【循環器内科・呼吸器外科・内科・心臓血管外科】
- 循環器内科・心臓血管外科・呼吸器外科を中心とした混合病棟である。
- 周手術期患者や心不全で入退院を繰り返す患者など、多職種で連携しパンフレットを使用した日常生活指導を行っている。また、70歳以上の患者が全体の77.4%を占めているため、認知症や日常生活自立度が低く生活援助を必要とする患者も多く、入院時より患者と家族の希望や意向を確認し、退院を見据えた看護実践を行うことで患者に応じた退院支援ができるよう努めている。
- 心電図を装着している患者が日々20名を超え緊張した毎日だが、全員で協力し話し合いながら笑顔で頑張っている。
7西病棟【外科、泌尿器科】
- 外科・泌尿器科48床の混合病棟である。周手術期を中心に、化学療法や透析、生体腎移植などの看護を行っている。
- 固定チームナーシングにおいては、泌尿器科急性期、外科急性期、混合の3つのチームに分かれ、担当する患者に対する看護目標を達成できるように努力している。多職種と連携をとりながら、患者・家族に寄り添い、少しでも安心して入院生活を送り、早期に退院できるよう看護スタッフ一丸となり取り組んでいる。
8東病棟【血液内科、眼科、呼吸器内科】
- 4床のクリーンルームを有する病棟である。血液内科と化学療法を主体とする呼吸器内科、及び白内障手術の眼科患者を受け入れ、多職種が一丸となって安全安心な医療の提供を目指している。
- 毎週水曜日は呼吸器内科、金曜日は血液内科の患者について、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、MSWと共に治療への援助や生活のあの決定などについて多職種でカンファレンスを持ち情報共有を行っている。
- 輸血学会の試験に合格した臨床輸血看護師を中心に、安全な輸血を行うとともに、医師や薬剤師と連携し、円滑に治療や処置をすすめられるように努めている。
- 病棟内の緩和ケア認定看護師を中心に、がん患者の精神的な看護や化学療法の副作用に関する看護を実践している。また、終末期にある患者に対しては、本人や家族の希望に添った最後が迎えられるように緩和ケアチームと連携し、多職種で協働している。
8西病棟【耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、外科】
- 外科・耳鼻科・眼科・皮膚科・形成外科の混合病棟であり、急性期から終末期までの看護を実践し、化学療法・放射線治療・手術療法など幅広い治療を行っている。様々な疾患の治療や看護を行っているため、アセスメント能力や技術、専門的知識が身に付き、広範囲にわたる看護について学びを深めることができる。
- 入院・転院数は他病棟と比較し最も多い病棟であるが、年間700件を越えたクリニカルパスを活用し、記録や時間外の短縮に取り組んでいる。
- 不安に寄り添い、思いを受け止めながら1人1人の希望する過ごし方を共有し、支える医療の提供向けて日々努力している。地域連携室やリハビリ、栄養士などの多職種と協同・情報共有し連携を図りながら、安心して生活できるようにサポートしている。
救命救急センター(ICU)
- 緊急度が高く、専門的なケアが必要な患者に柔軟かつ個別性のある質の高い看護が実践できるようICU内のクリティカルケア特定認定看護師・教育担当看護師を中心に定期的な勉強会の実施、OJT教育、新人看護師や異動者教育など継続的にスキルアップできるような教育体制を構築している。クリティカルケア特定認定看護師の活動として、呼吸・鎮痛鎮静・栄養・感染など各種カンファレンスでのファシリテーションや早期栄養介入管理加算算定に向けた取り組みになど多職種と協働している。またICU内の教育だけでなく、看護専門学校での講義、院内研修・新人研修の講義担当や院内BLS教育などに携わっている。
- 2023年7月~早期栄養介入管理加算が開始となり、対象患者の病態・状態に応じた栄養管理計画や治療目的を多職種全体カンファレンスで共有・アセスメントを行い、早期栄養管理介入に取り組んでいる。
- 固定チーム活動では、せん妄予防ケアリストを作成し、せん妄予防や発生後の期間短縮に向けた取り組みや挿管患者対象に栄養カンファレンスの充実・至適カロリー摂取に着目した看護実践に取り組んでいる。
救命救急センター(HCU)
- HCUでは、重症患者の受け入れを行っている。診療科は多岐にわたり多種多様な患者の入室がある。
- 急変にも迅速に対応ができるように24時間モニタリングを行っている。
手術室
- 手術室は、バイオクリーンルームを含め7室で運用している。年間、4600件程度の手術件数である。24時間体制で緊急手術を受け入れており、全手術症例の約21%が緊急手術である。夜間・休日は、オンコール自宅待機制で、全診療科の手術に対応できる体制を整えている。
- 手術室内の感染管理認定看護師を中心に、手術環境を整え、感染防止に努め、手術に携わるすべての職員に対する教育指導も継続的に行えている。新型感染症の緊急手術の受け入れも経験し、受け入れ体制も構築している。
- 近年手術患者の高齢化が進み、複合的な疾患を持ち、術後合併症のリスクも高い患者の対応も行っている。患者、家族の安全と安心を意識した周手術期看護を提供できるように取り組んでいる。
外来
- 診療科は35科、積極的にかかりつけ医との連携を進め、地域支援病院としての役割を果たしている。
- 各診療科での専門外来を含めた診療の補助、外来化学療法、ストーマ外来、糖尿病透析予防指導など看護師の専門性を活かした患者介入も行っている。
- 眼科外来手術、糖尿病患者への外来でのインシュリンやリブレ導入指導、がん患者へのICサポートなど緩和ケア認定看護師と協力し、外来看護師の役割拡大を行っている。また小児科の虐待対応については臨床心理士と共に介入している。
透析室
- 17床の病床で透析を行い、年間延べ4000名近くの血液浄化治療を実施している。
- 透析技術認定士の資格を取得した看護師を含めた看護師6名と、今年度より臨床工学技士3名が透析室専任として従事することになり、協力して業務に取り組んでいる。
- 透析導入期から患者・家族も含め、食事管理・日常生活指導を行っている。また毎月1回医師・看護師・臨床工学技士・栄養士にて多職種カンファレンスを行い、患者の情報共有と共に、専門的知識の向上、看護の質の向上に努めている。
内視鏡室
- 内視鏡技師3名、小腸カプセル内視鏡読影支援技師1名を含む看護師9名、看護助手1名のスタッフで各種検査・治療の介助、前処置、検査後患者のリカバリー管理、内視鏡機器管理、感染対策、処置具などの物品管理を行っている。担当医師と協働して、安全で確実な検査・治療を心掛けている。
- 年間、上部消化管内視鏡検査約4,000件、下部消化管内視鏡検査約2,000件、胆膵系処置約350件を行っている。上下部消化管粘膜剥離術(ESD)約100件や大腸ポリープ切除、約500件など検査・治療を実施している。2022年4月より呼吸器内科が開設され気管支鏡の検査・処置を年間約120件実施している。COVID-19患者の対応は、マニュアルを活用して感染対策を実施している。
- 休日・夜間の緊急内視鏡への対応として、看護師の待機制を導入し、年間約100件程度対応している。
- スタッフは、Web研修や消化器内視鏡学会・講習会等積極的に参加し自己研鑽に努めている。また得た知識を共有し業務改善などにも役立てている。
化学療法室
- 化学療法室では、年間約4000件、月平均約350件、1日平均約16件の化学療法を実施しており、外科(大腸がん)、呼吸器内科(肺がん)、乳腺外科、血液内科の治療が全体の約51%を占めている。分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬などの新規薬剤や皮下注射製剤の開発に伴い、高齢者やADL介助が必要な患者の外来治療も増えている。
- がん化学療法看護認定看護師を中心に、安全かつ確実な薬剤の投与管理を実施し、起こり得る有害事象の予防や軽減、苦痛の緩和に努めるとともに、患者が安心して治療が継続できるように電話相談や外来相談に対応している。また、自宅での療養生活や通院治療に伴う困りごとへの介入やサポートなど、多職種連携によるチーム医療の提供にも取り組んでいる。
- 病棟看護師の協力のもと、病棟と外来の連携を図り、外来治療移行患者のテンプレート記入や化学療法室見学などを行い、患者情報の共有や看護の継続に努めている。
救急外来
- 南予の救命救急センターの窓口として、救急外来を受診する患者の初期対応に尽力している。
- 救急搬送患者のすべてが、重症で緊急性が高い状態とは限らないため、院内トリアージを実施し、緊急度、重症度を的確に判定し、緊急度の高い患者を早期に診療や治療に繋げられるように救急外来内のマネジメントも同時に行うようにしている。
- 急変対応、院内トリアージ、外傷看護など専門性の高い看護実践が行える救急看護認定看護師やDMAT隊員、トリアージナースも配置されており、他のスタッフも自己研鑽に励み受診患者の安全を確保する努力を行っている。
- 生命の危機的状況に遭遇する機会も多く、ストレスフルな状況ではあるが、『穏やかな海で良い船員が育つことはない』という英国のことわざにもあるように素晴らしい人材が育つ部署である。
放射線科
- 放射線科では、診断検査、血管内治療、CT検査、MRI検査、RI検査、放射線治療を行っている。X線テレビ室では、CVC、ポート植え込み、上部下部消化管造影、その他透視検査を実施している。血管造影室では、脳外科、放射線科、泌尿器外科の血管造影検査・治療、循環器内科の心臓血管治療・検査を実施している。
- 夜間休日は、待機制をとっており、年間約70件程度の緊急血管造影検査及び治療を実施している。
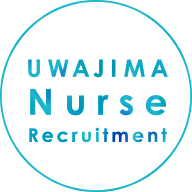
 エントリー
エントリー